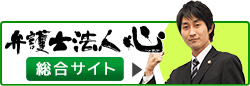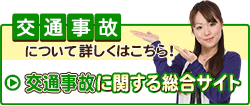1 いつまでに示談をしなければならないのか
相手方保険会社から被害者に対して示談の提案をしてきた際に、短期の回答期限が記載されていて、急に示談を迫られることがあります。
示談提案をされて和解をするかどうかは、被害者の自由です。
あくまでも保険会社からの提案にすぎませんので、保険会社が勝手に決めた回答に期限を過ぎたとしても、賠償金の請求自体ができなくなるわけではありません。
もちろん、期限後に提案金額を変更される可能性はありますが、提案金額も回答期限自体も保険会社からの提案に過ぎないため、被害者がそのまま受け入れる義務はないのです。
保険会社の提案は、過失割合や示談金額について交渉の余地が残されていることが多く、内容を精査せずに焦って和解して示談書を返送してしまうと撤回することは困難ですので、被害者の不利な示談になることがあります。
保険会社から提案があっても、まずは落ち着いて、書類の返送をせずに弁護士などの専門家に適切かどうかを相談してみてください。
2 損害賠償請求の期限
極端な話、時効の成立まではいつでも損害賠償請求はできますので、相手保険会社にせかされても焦る必要はないです。
しかし、いつまでも保険会社や加害者に請求をしないままにしておいても大丈夫なのかというと、時効による請求権の消滅という危険はあります。
基本的には一般的な交通事故の損害賠償請求権の時効期間は、早ければ、物的損害については交通事故発生の翌日から3年、人的損害については交通事故発生の翌日から5年で、時効を援用される可能性がでてきます。
また、自賠責保険への被害者請求の時効は3年です。
時効がどの時点から開始するか等は、弁護士等にきちんと事情を説明して確認した方がよいですが、損害賠償請求が可能になったらできるだけ早く交渉を開始したほうが証拠なども残っているので安全です。
焦って示談をする必要はありませんが、交通事故の損害賠償請求が可能になったら、放置せずに請求を開始しましょう。
3 時効の完成猶予や更新
なんらかの理由で時効の完成が近づいている場合には、時効の更新や完成猶予といった措置をとることで、時効の完成を妨げることができます。
時効の更新は、法律で定められた時効の更新事由が認められた時点で、それまでの時効期間を一旦白紙に戻し、改めて時効期間のカウントを開始する制度です。
時効の完成猶予は、法律で定められた時効の完成猶予事由が認められた時点で、時効期間を一時的に停止する制度です。
いずれの制度も、すぐに対応できるとは限らないため、時効の完成が近づく前に弁護士に相談してください。
4 交通事故に詳しい弁護士への相談
交通事故の損害賠償請求は、適切な過失割合や提案金額かどうか、いつまでに請求しなければならないかなど、弁護士に相談したほうがよいことがたくさんあります。
また、治療が長期化している際には、時効について注意をしなければならないこともあります。
交通事故の被害者は、交通事故に詳しい弁護士にお早めに相談をしてください。