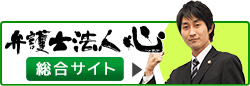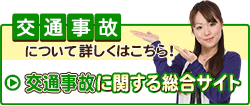1 自転車の飲酒運転と罰則
京都も年末が近づき寒さが厳しくなってきました。年末が近づいてきたことで、飲酒する機会も増えてきます。
自動車の酒気帯び運転はもちろんのこと、自転車の酒気帯び運転も刑事罰の対象です。
もともと自転車の飲酒運転自体が禁止はされていましたが、2024年11月1日施行された道路交通法の改正前はいわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でした。
自転車の酒気帯び運転は、道路交通法の改正により、現在は、3年以下の懲役又は50万円以下罰金に罰則が強化され、車両の提供者、酒類の提供者、同乗者にも罰則規定されました。酒気帯び運転は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為をいいます。
自転車の酒気帯び運転について改正道路交通法が施行されてそろそろ1年が過ぎ、実際の運用が明らかになってきています。
2 自転車の酒気帯び運転の実例
自転車の酒気帯び運転について、実際はどの程度が摘発されるのか実効性を不安視していた方もいましたが、各地でかなり多くの自転車運転者が摘発されています。また、行政処分を受ける実例や、自転車の酒気帯び運転で実刑が言い渡される実例も出てきています。
軽い気持ちでお酒を飲んだ後に自転車に乗ってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、これから年末にかけて、酒気帯び運転での自転車運転者の摘発は増加してしていくことが予想されます。
お酒を飲んだ後には判断能力や運動能力が低下し、大きな事故につながってしまいます。自転車事故でも被害者に重大な傷害を負わせることもありますし、自分自身が重大な傷害を負ってしまうこともあります。
お酒を飲んだ後は、自動車の運転は勿論のこと自転車の運転も絶対にやめてください。